あなたの会社が納めるべきかどうか、3つのカギでチェック!
💡はじめに
会社の設立や事業の拡大を考えるとき、「税金」は切っても切り離せないテーマです。法人が負担する税金の中には、「地方法人税」や「法人事業税」など様々なものがありますが、その中でも利益の有無にかかわらず課税されるのが、地方税の「均等割」です。
「赤字なのに払わなきゃいけないの?」
「そもそも自宅兼オフィスでも課税される?」
こうした疑問について、日々の業務の中で調べる機会がありましたので、備忘も兼ねてまとめてみました。
今回は、均等割の課税対象となるかどうかを判断する「事務所または事業所」の3つの要件について、わかりやすく整理しています。
✅そもそも「均等割」とは?
均等割とは、法人が地方自治体(都道府県・市町村)に納める地方税の一種で、法人の資本金や従業員数、そして事業所の所在などに応じて、一定額が毎年課される税金です。
事業の赤字・黒字に関係なく、一定の条件を満たすと課税されます。
✅課税対象となる3つのカギ(要件)
均等割が課税されるかどうかの判断は、「事務所または事業所を有するか」という点で決まります。そのための判断基準となるのが、次の3つの要件です。
① 物的設備:場所があるかどうか
事務所または事業所とは、事業活動の拠点となる「場所」のこと。自社所有でなくても、以下のような条件を満たせば「物的設備あり」と判断されます。
- 賃貸オフィスや店舗
- 自宅の一部を使っている場合(いわゆるSOHO)
- 椅子・机・パソコンなどの備品がある
✅ポイント:所有かどうかは関係ない!
「事業活動を行うために必要な場所があるか」が重要!
🔍こんな時はどうなる?プラスα
たとえば、創業当初は自宅を登記住所にしていて、一室を使って仕事をしていたけれど、現在は別の場所を借りてそちらで業務を行っている。
自宅ではもう仕事はしていないが、登記はそのままになっている…。
こんなケース、よくあるのではないでしょうか?
実際、今回私が対応したケースもまさにこのパターンでした。
✅結論:事業を行うための場所でなければ、課税対象にはなりません。
つまり、自宅は現在「事業活動を行うための場所」ではないため、自宅に対しては均等割の課税なし。
一方で、実際に業務を行っている新しい事務所に対して、均等割が課税されることになります。
② 人的設備:人がいるかどうか
続いては、その場所に人がいるかという点です。
ここで言う「人」とは、正社員だけに限らず、以下も含まれます。
- 役員
- パート・アルバイト
- 派遣社員(自社の指揮命令下にある場合)
そして、「人がいる」とは、単に常駐しているケースだけでなく、次のような場合も含まれます。
- 定期的にその場所で働いている
- 不定期でも、かなりの頻度で事業活動に従事している
✅ポイント:「常駐」していなくても、継続的に従事していればOK!
③ 事業の継続性:一時的でないか
最後は、その場所で事業を継続して行っているかどうかです。
以下のようなケースは「継続性あり」と見なされます。
- 年度を通じて使用している
- 数ヶ月以上にわたって定期的に使用している
一方で、以下のような場所は「継続性なし」と判断されることがあります。
- 短期的な仮設事務所(例:建設現場の詰所など)
- 一時的な会議・休憩スペース
✅ポイント:一時的・臨時的な場所は除かれることもある!
📘根拠条文
- 地方税法第24条第1項第1号(都道府県民税の均等割)
- 地方税法第314条の2第1項第1号(市町村民税の均等割)
- 総務省自治税務局「地方税務処理要領」 等
💬まとめ:3つの要件を総合的に判断!
均等割の課税対象かどうかは、「物的設備」「人的設備」「継続性」の3点を総合的に判断して決められます。
- ✅ 自宅でも課税対象になることがある
- ✅ 人材派遣も要件に含まれることがある
- ✅ 一時的な事業所なら非課税になることも
「うちの会社の場合はどうなんだろう?」と迷ったら、事業所を置く予定の自治体の税務課に確認するのが一番確実です。無料で相談できますよ!
⚠️免責事項
本記事は、地方税法および通達に基づいて筆者が独自に調査・学習した内容をもとに作成しています。
税務判断は各法人の具体的な状況により異なりますので、実際の申告・手続きにあたっては、必ず税理士・自治体の担当部署等の専門家にご確認ください。

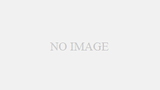
コメント