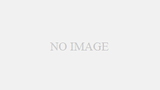はじめに
今回は役員の退職金を支給するというケースがあり、退職金を支給するにあたり退職金支給後の役員報酬の設定をしなければならない事案があったため、調べる機会がありましたのでまとめます。
また、退職金支給後の役員報酬設定金額を考える上で重要なことは、「退職した」と税務上認めさせることであり、それによって退職金の損金算入が否認されないようにすることが大切です。
気をつけるべきことは他にもありますが、今回は**「役員報酬の設定」**について焦点を当ててまとめます。
退職金は会社の損金になるの?
会社が支払う役員退職金は原則として損金算入が可能です。損金にできれば法人税が減少するため、会社にとっては重要な税務戦略となります。
ただし、税務上は「実質的な退職」と認められる必要があり、その判断にあたっては退職後の役員報酬の金額が重要な要素となります。
ポイントとなる通達:「分掌変更等による退職給与」
国税庁の法人税基本通達9-2-32では、以下のように定められています。
法人の役員の分掌変更又は改選による再任等があった場合においても、その役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められる場合には、退職給与として取り扱うことができる。
(中略)
(3)分掌変更等の後におけるその役員の給与がおおむね50%以上の減少をしたこと。ただし、その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。
このように、報酬が50%以上減少しているかどうかが、実質退職か否かを判断する一つの基準とされています。
どれくらい減らせばいいの?【税務上の目安】
- 最低ライン:報酬を「50%以上」減額
通達に定められた基準であり、満たさなければ退職金の損金算入が否認されるリスクがあります。 - より安全な設定:報酬を「70%前後」減額
実際の判例でも、元の役員報酬の70%近くを減額したケースがあり、形式的基準より大幅な減額が認められた一因と考えられます。
【参考判例】争点は退職金だが報酬減額が問題視されなかった例
▶ 東京高等裁判所 平成25年7月18日判決(平成24年(行コ)第136号)
事案の概要
会社が元代表取締役に対して支給した退職慰労金について、その一部を損金算入したところ、税務署が「不相当に高額」として一部を否認したため争われた事案です。
判決のポイント
- 役員は代表取締役を退任し、取締役会長に就任
- 報酬は従前に比べて50%以上減額
- 裁判所は、退職慰労金の金額の妥当性は否定したが、報酬の減額については特に問題視しなかった
実務上の意義
この判例は、報酬減額の水準が通達基準を満たしていれば、その後の役員報酬の設定が問題視されない可能性を示す実例といえます。
まとめ:税務上「退職」を成立させるための役員報酬設定のポイント
根拠条文・通達
- 法人税法施行令 第70条(退職給与の損金算入)
- 法人税基本通達 9-2-32(役員の分掌変更等の場合の退職給与)
免責事項
本記事は、筆者が税務を学ぶ過程で調査・整理した内容を、勉強用の備忘としてまとめたものです。
記載内容は一般的な解釈に基づいており、個別事案にそのまま適用できるとは限りません。
実際の税務判断・処理については、必ず税理士などの専門家にご相談のうえご対応ください。
本記事の内容に基づいて発生した損害等について、筆者は一切の責任を負いません。