今日は、相続税法でよく出てくる「扶養義務者」について勉強しました!
■ 法律で決まっている人たち
- 配偶者
- 親・子・孫などの直系血族
- 兄弟姉妹
- 家庭裁判所の判断で扶養義務があるとされた三親等内の親族(例:おじ・おばなど)
■ 実際に一緒に暮らしている人も!
たとえ家庭裁判所の判断がなくても、生計を一にしている三親等内の親族は「扶養義務者」として扱われるそうです。
つまり、いっしょに生活してたらOKってこともあるみたいです。
■「生計を一にする」ってどういうこと?
税法ではよく「生計を一にする」という用語が出てきます。そこで用語の意義について調べて見ました。
所得税の通達(2-47)によると:
- 必ずしも同居は必要ない
- 仕事・学校・療養で別居でも、生活費や学費を仕送りしていればOK
- 休みに一緒に過ごすことが常例ならOK
- 逆に、同居していても完全に別々に生活していれば対象外
とのこと。
つまり、物理的な距離ではなく、「生活のつながり」が大切。
実態が大切と実務でよく聞くことがありますが、まさにそれですね。
■ 三親等ってどこまで?
今回の通達に出てきた「三親等内の親族」が気になったので調べてみました。
- 祖父母、孫(これらは二親等)
- 叔父・叔母、甥・姪(これらは三親等)
- 曾孫(これも三親等)など
※配偶者側の親族(姻族)も、三親等内であれば対象になることがあります。
よく「何等身」なんて言い方を聞くことがありますが、法律では「何親等」で表現されていて、こういう範囲のことなんだと改めて知りました。
■ 判定のタイミング
- 相続税: 相続が開始した時点(死亡時)
- 贈与税: 贈与があった時点
■ なるほどポイント
法律上の関係だけでなく、実際の生活のつながりも重視されている点が印象的でした。
「実態に即する」というところが大事なのかなという印象です。
■ 引用元
■ まとめ表
誰が扶養義務者に当たるか
| 区分 | 扶養義務者か | 補足・根拠 |
|---|---|---|
| 配偶者 | ○ | 民法上当然に扶養義務あり |
| 直系血族(親・子・孫など) | ○ | 民法第877条により明確に扶養義務あり |
| 兄弟姉妹 | ○ | 同上 |
| 三親等内の親族(おじ・おば等) | △ | 家庭裁判所の審判 or 生計を一にしていれば該当 |
| 四親等以遠の親族 | × | 法律・通達上、扶養義務者には含まれない |
判定の時期
| 税目 | 判定時点 |
|---|---|
| 相続税 | 相続開始時(死亡時) |
| 贈与税 | 贈与の時 |
※免責事項
本記事は、税務に関する一般的な制度・知識を学習・共有する目的で作成したものであり、個別の税務相談には該当しません。
内容には十分注意を払っていますが、正確性・最新性・適法性を保証するものではありません。
実際の税務判断にあたっては、必ず税理士等の有資格者にご相談ください。
引用元として明示された資料の著作権は、それぞれの発行元に帰属します。

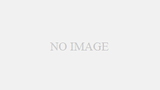
コメント